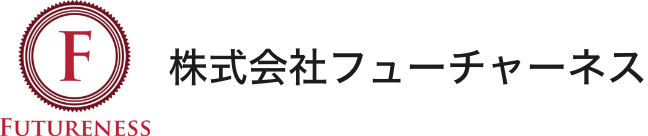フォーカルクエスチョンにエッジを効かせる【シナリオプランニング技法】
弊社の新しいお客様と共同で実施する、都内大学院社会人向けMBAコースでのシナリオ研修プログラムが始まりました。弊社お客様は大学院の先生。研修生はパートタイムMBAプログラムの社会人学生たち。5~7月にかけて日曜日の9時~17時を3回。テーマに沿ったシナリオを作りながら、イノベーションのためのシナリオプランニングを学ぶ、というプログラムです。研修生の皆さんは、それぞれシニアなポジションの方も含めた社会人たち。日曜日にこれだけ長丁場の研修を受けると、月曜日から相当疲れそうですが、第1回目は皆さん集中して参加されていました。
さて、シナリオプランニングにおいては、設計段階で「フォーカルクエスチョン(Focal Question)」を設定し、プロジェクトを通じてその問いに答えるべくアプローチをします。本研修プログラムで、この「フォーカルクエスチョン」の設定に関する気づきがありましたので、共有いたします。
「フォーカルクエスチョン」とは
「フォーカルクエスチョン」とは、その英語の示すように「焦点をあてる問い」です。
このシナリオ検討で一体どのようなクライアントの問題意識にアプローチするのか?どんな問いに答えたいのか?
それを疑問文で表現し、シナリオのクライアントやシナリオ作成ワークショップの参加者との共通認識にします。
例えば、「当社の〇〇事業を取り巻く△△年の事業環境は、どのようになり得るか?」といった形です。
問いにエッジを効かせる場合とは?
この研修では、ある業界の現存するメーカー企業(研修生の企業ではない)をモデルとして、シナリオ作りの練習をしました。そのため、私が用意していたフォーカルクエスチョンはまさに上記のような「当社の〇〇事業を取り巻く△△年の事業環境は、どのようになり得るか?」だったのですが、本講座を主宰されている先生から、フォーカルクエスチョンは「事業環境がどうなるか、ではない。その問いには答えようがない」と指摘があり、はっとしました。
先生からは、フォーカルクエスチョンは「面白そうだな」と思えるシナリオのテーマであり、答えがシナリオから出てくること。勝者は?リスクは?投資すべき領域は?ある領域に参入すべきかどうか?などである、とのコメントがありました。
私が過去に実際に複数の民間企業において実施してきたシナリオ検討では、「未来の事業環境はどうなっているか?」という探索的な問いを設定することが多かったのです。この問いには答えようは実はあり、シナリオナラティブを通して未来の事業環境を仮想体験させます。それがシナリオの力です。
一方、事業環境の探索よりも、ある意思決定のためのシナリオ検討もあるでしょう。この場合、より焦点を狭めた問いを設定することになります。
また、面白い問い、エッジを効かせた問いを設定することで、シナリオプロジェクトに参加する人たちの知的好奇心を煽る、という効果もあるでしょう。「問いのデザイン」を執筆された安斎勇樹さん、塩瀬隆之さんは、本書の中で以下のように述べています。
強調しておきたいことは、問いは人の思考だけでなく、感情をも刺激するという性質です。人は何かを問われたら、答えるために考えようとする。(中略)けれども、人を「考えたい」と動機づけることは、簡単なことではありません。楽しさや好奇心、驚きなどの感情を刺激することは、「わかったつもり」を打破し、日常で凝り固まった認識を揺さぶるきっかけづくりとして、とても有効です。
安斎・塩瀬 (2020)「問いのデザイン」p24
フォーカルクエスチョン設定の実践
前回のコラムで「良いシナリオ」の条件(以下)を説明しました。
- Prausible(なるほど、起こり得る、とオーディエンスが腹落ちできる)
- Challenging(今までに聞いたことがない目新しさや、敢えて直視することを避けてきた展開が含まれている)
- Relevant(クライアントの関心領域に応えている)
フォーカルクエスチョンは、3番目のRelevantと大きく関わってきます。
シナリオ検討をそもそも実施したいのは、クライアント(例えば企業であればその担当分野の役員等)です。しかし、クライアント自身も、どのようなシナリオ検討をしたいのか、イメージはあってもはっきり言語化できていない場合があります。
クライアントへのインタビューを通して、問題意識(問い)を言語化していく。そしてその言語化したものを文書(プロジェクト定義書)で残してクライアントと「これでいいですね?」と確認、共有化しておく。このプロセスが大事です。また、フォーカルクエスチョンはワークショップ当日、参加者に提示し、参加者も同じ船に乗っていることを担保します。
まとめ
本稿をまとめます。
- フォーカルクエスチョンは、シナリオテーマとスコープをつなぐもの。そのシナリオプロジェクトで答える問い
- クライアントとプロジェクト定義書の中で合意すべき。良いシナリオの3要件である「Relevance」を担保
- クライアントがいない研修等では、講師から与えられたり、研修生内で決定したりする
- 大事なことはクライアントの合意。合意ができていればどんな問いでもよい。ただ、敢えてエッジを効かせて参加者の知的好奇心を刺激するのも一考。「問いは、思考と感情を刺激する」