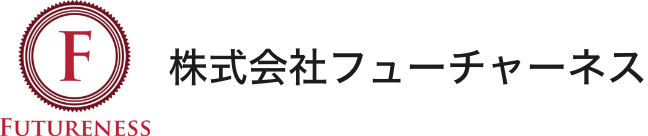シェルのエネルギー変革シナリオ(2)
シェルが2021年に公開した最新のグローバルエネルギーシナリオ「エネルギー変革シナリオ(The Energy Transformation Scenarios)」を読み解いています。第2回目の今回は、いよいよ、Waves、Islands、Sky1.5の3シナリオの内容をご説明します。
- 原典はこちら → The Energy Transformation Scenarios (2021)
- 第1回目はこちら → シェルのエネルギー変革シナリオ(1)
三つのシナリオ
「エネルギー変革シナリオ2021」は、Waves、Islands、Sky1.5という三つのシナリオから構成されています。以下にその概要をご紹介します(英語原典を元に筆者が日本語に概要解説したものです。公式の日本語訳ではありません)[1]
「Waves」シナリオ -始まりは遅いが、その後急加速する脱炭素化-
Wavesでは、コロナ禍からの回復において経済復興が優先される。「豊かさ第一」の世界。
人々は経済指標によって利益の大小を測り、経済力ある社会こそレジリエントだと考える。経済回復は早いのだが、早期活動再開の代償としてコロナ感染が波となって何度も到来する。経済回復に伴って、エネルギー需要、化石燃料需要、そして温室効果ガス(GHG)排出量も急増。
しかしこの回復の波をいずれは打ち砕くことになる下層流もまた、水面下でうごめいているいるのだ。見た目の経済回復によって、格差の拡大や社会不満といった、より深い社会課題が覆い隠されてしまう。経済力の強化は、次なるショックへの経済的バッファとして「構造的なレジリエンス」となるが、本来必要だったはずの構造改革は先送りとなる。
やがて、放置されていた構造的な社会課題が頭をもたげ始める。公衆衛生・健康、社会福祉、気候変動といった問題によって社会や環境面でのストレスが高まっていくと、社会的・政治的に大きな揺り戻しが起こる。頻度と激しさを増した異常気象に対する人々の反応は厳しさを増し、政治が、がむしゃらになるのだ。ここに至って、化石燃料の利用を強制的に削減する強い政策が導入される。これによって、世界の石炭及び石油需要は2030年代にピークアウトし、天然ガス需要すらそう長くは続かない。
ようやく急速な脱炭素化の動きが始まるが、「2℃を下回り1.5℃を目指す」というパリ合意の目標達成には、時すでに遅し。世界のCO2ネットゼロ排出に到達するのは2100年頃となる。産業革命前と比較した気温上昇は2.3℃に達する。
「Islands」シナリオ -遅く始まり、進みも遅い脱炭素化-
Islandsでは、各国政府や社会は、自分たち自身の安心・安全確保に集中する。「セキュリティ第一」の世界。
様々な国でナショナリズムが強調され、第二次大戦後の地政学的秩序にとっての脅威となっていく。このシナリオでのレジリエンスは島国根性的で、自治権や自給自足が重視される。次なる国際的なショックに対して自国を守るため、他国とのシステムの繋がりを薄めるべく、重要物資や食糧、エネルギーの対外依存度を低めようというわけだ。しかしその成果はまちまちで、ある国では成功するが、別の国では政策の非効率さに苦しむことになる。
国際貿易摩擦は激化し、世界経済の成長は徐々に停滞していく。気候変動に対処するための国際努力も鈍化してしまう。パリ合意のプロセスはバラバラに壊れ、各国が短期的な経済成果に注力する結果、安価な化石燃料への依存体質が続いていく。世界のCO2排出量はゆっくりにしか減っていかない。やがて異常気象が混乱をもたらし人々は苦しむが、その非難は他国に向かってしまう。
それでも通常の技術進化速度によってエネルギー利用機器やインフラが高効率化していき、クリーン技術も普及していくので、GHG削減はやがて進み、22世紀に入ればネットゼロに至る。しかしパリ合意のタイムラインはとうに過ぎ、目標達成はできない。今世紀末の気温上昇は2.5℃に達して止まらず、ゆっくりと上昇を続ける。
「Sky 1.5」シナリオ -今すぐ加速する脱炭素化-
Sky1.5では、コロナ禍への対応は、世界大での流行(パンデミック)の解決と公共の福祉が抱える課題解決へと向かう。「健康第一」の世界。
パンデミックの解決は容易でなく、各国が連携した感染封じ込め努力とワクチン開発に向けた健全な競争が求められる。この“手ごわさ”が各国政府を真剣にさせ、実務的な協働を促す。パンデミック対応が成功事例となり、様々な社会課題に対処するにあたって、一致団結した協働関係の価値が、深く広く、社会に認識されていく。
コロナ禍からの経済復興と経済グリーン化の同時達成を目指すグリーンニューディール政策を各国が学び、展開していく。米国、中国、そしてアジアや欧州の技術立国諸国において、クリーン技術の開発・普及目標と、国内産業振興・産業競争力強化を目指した経済目標が、併行して目指されていく。
世界経済の急速かつ広範な電力化が進み、その発電を担うのは再生可能エネルギーだ。世界の石炭及び石油需要は2020年代にピークを迎え、天然ガスも2030年代にピーク化する。電化が困難なセクター(航空輸送や化学産業など)では、化石燃料からバイオ燃料や水素といった非化石燃料へと漸進的に置き換わっていく。先進諸国では2050年までにネットゼロを達成。世界はパリ合意の目標達成に向かっていく。一時的に1.5℃を上回るのだが、その後、CO2除去によって今世紀末の気温上昇は1.5℃となる。
どのシナリオも同じ確率で起こりそうに思えるが
さて、「エネルギー変革シナリオ2021」に描かれた3つのシナリオ概要をお読みになり、どのような感想をお持ちでしょうか?筆者には、政治・社会経済における将来の展開、それがどのようにエネルギー利活用と気候変動に異なった影響を及ぼすのか、シェルらしい分析と語り口で記された、読み応え、分析がいのあるシナリオ作品であるように感じます。
シェルが確立したシナリオプランニング手法において、大切にされている考え方があります。それは「どのシナリオも同じような確率で起こり得ると思える(equally plausible)」ように、シナリオを作る/語る、という考え方です。
なぜ、この考え方が大切なのか?それはシナリオプランニングの目的は、将来予測ではないからです。シナリオプランニングの目的は、聞き手の視野を拡げ、今まで視界に入っていなかった将来の変化の可能性を認識させること(それにより、今まで思ってもいなかった将来のリスクや機会の発見につなげること)だからです。もし、3つのシナリオのうち、1つのシナリオが起こる確率が75%である、と語ったとします。それは将来予測に他なりません。そしてシナリオの聞き手は、当然、より発生確率の高いシナリオに意識が集中し、残りのシナリオへの注意がおろそかになるでしょう。未来のことなど分からない。それがシナリオプランニングの基本姿勢です。
しかし、本シナリオの序文で、シェルCEOのベン・ファン・ブールデン氏は、こう述べています。
So, as you read this report, I would like to ask you to keep one thing in mind: each of the three futures set out here is possible, but only one of them presents a truly desirable destination. Sky 1.5 is that scenario.
Ben van Beurden, CEO, Shell (2021)
どのシナリオも起こり得る可能性があるが、パリ協定の目標を達成する Sky 1.5だけが唯一、真に望ましい方向性なのだ、とのこと。ここに世界的なエネルギー企業であるシェルの価値観やビジョンが表れています。このような望ましいシナリオのことを「規範的なシナリオ」と呼びます。一方、将来の様々に異なる展開を探るシナリオを「探索的なシナリオ」と呼びます。規範的なシナリオと探索的なシナリオは、一つのシナリオ作品に共存することができます。「エネルギー変革シナリオ」の3シナリオのうち、Sky 1.5が規範的シナリオ、Waves、Islandsが探索的シナリオと考えられます。
なお、前作のグローバルエネルギーシナリオの「ニューレンズシナリオ」では、Mountains、Oceansとも探索的であり、規範的シナリオは存在しませんでした。少し遡って、2001年(Business Class & Prism)、2004年(Open Doors, Flags, Low Trust Globalization)のいずれのグローバルシナリオにも規範的シナリオは存在しません。グローバルシナリオとエネルギーシナリオがニューレンズシナリオとして統合される前のエネルギーシナリオ「Scranble & Blue Prints」ではBlue Printsが規範的でした。シェルのグローバルシナリオとして規範的シナリオが採用された例は少ないですが、2018年「Skyシナリオ」以降、シェルは規範的シナリオを活用し続けています。探索的、規範的シナリオに関する説明は、別途ご説明することにします。
エネルギーに詳しい読者の方への驚きは、ひょっとすると、3つのシナリオのいずれにおいても、やがて世界のCO2排出量はネットゼロに至る、というシェルの分析かもしれません。この点について、次回コラムでご説明いたします。
(3)に続く
[1] シナリオ詳細は、原典(Shell (2021) The Energy Transformation Scenarios)、や角和(2021)「エネルギー変革シナリオ2021」石油・天然ガスレビュー https://oilgas-info.jogmec.go.jp/review_reports/1008941/1009043.html をご参照のこと。